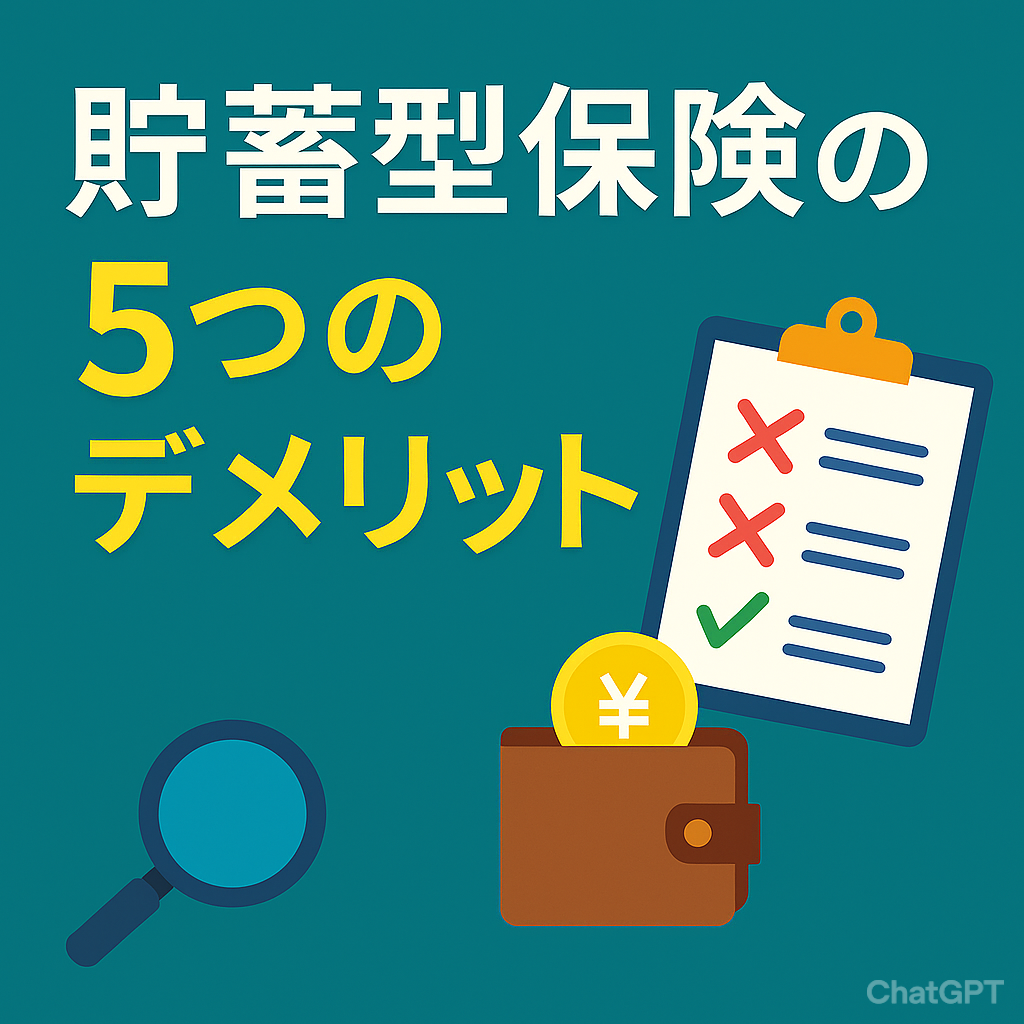5秒でわかる結論
- 貯蓄型保険の利回りは年0.1〜0.5%(銀行預金とほぼ同じ)
- 18年で返戻率102%=つみたてNISAなら162%
- 元本割れしても解約してつみたてNISAに切り替えた方が得
「貯蓄型保険は安全で確実」と信じていませんか?実は、保険会社と銀行だけが儲かる仕組みになっています。この記事では、貯蓄型保険の5つの致命的なデメリットを、実体験と具体的な数字で解説します。
あなたは大丈夫?貯蓄型保険で損している人チェックリスト
- 学資保険に月1万円以上払っている
- 「貯蓄型保険は元本保証だから安心」と思っている
- 返戻率が100%を超えていれば得だと思っている
- 途中解約すると損だから続けている
- 保険の営業マンに「これが一番安全」と言われて加入した
- つみたてNISAと比較したことがない
2つ以上当てはまる方は、この記事を最後まで読んでください。
10年後に100万円以上の差がつく可能性があります。
貯蓄型保険とは?【4つの種類を解説】

貯蓄型保険とは、保障と貯蓄の両方の機能を持つ保険のこと。解約時や満期時にお金が戻ってくるのが特徴です。
貯蓄型保険の種類
保険の種類と概要(比較表)
| 種類 | 目的 | 満期・返戻率 | 月額保険料目安 |
|---|---|---|---|
| 学資保険 | 子どもの教育資金 | 18〜22年 / 100〜105% | 1〜2万円 |
| 終身保険 | 死亡保障+老後資金(一生涯) | 一生涯 / 105〜110% | 1.5〜3万円 |
| 養老保険 | 貯蓄+死亡保障 | 10〜30年 / 100〜103% | 2〜4万円 |
| 外貨建て保険 | 高利回り狙い | 10〜30年 / 110〜130%(変動) | 2〜5万円 |
※上記は目安です。商品や契約条件により金額・返戻率は変わります。
一見すると「お金が増えて戻ってくる」ので魅力的に見えますが、実は大きな落とし穴があります。
貯蓄型保険の5つの致命的なデメリット
デメリット①:利回りが低すぎる(年0.1〜0.5%)
具体例:典型的な学資保険
具体例:典型的な学資保険
| 月額保険料 | 10,000円 |
| 払込期間 | 18年 |
| 払込総額 | 2,160,000円(10,000円×12ヶ月×18年) |
| 満期金 | 2,200,000円 |
| 返戻率 | 101.8% |
| 実質利回り(年) | 約0.1% |
※計算は概算です。手数料・税金等は考慮していません。
これって本当に得なの?
銀行の定期預金(年0.002%)よりはマシですが、インフレ率(年1〜2%)を考えると実質マイナスです。
他の運用方法との比較
18年後の金額比較(運用方法別)
つみたてNISAとの差額:130万円
同じ月1万円を積み立てても、18年後に130万円も差が開くのです。
デメリット②:途中解約で元本割れする
貯蓄型保険の最大の罠が**「途中解約すると元本割れする」**という点です。
具体例:学資保険を10年目で解約した場合
学資保険 10年分の払込・解約返戻金と損失
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 払込総額(10年分) | 120万円 |
| 解約返戻金 | 90万円 |
| 損失 | ▲30万円 |
| 損失率 | 25% |
なぜこんなに減るのか?
保険会社は契約時に以下のコストを差し引いています。
- 営業マンの人件費・手数料(約10〜15%)
- 保険会社の運営コスト(約5〜10%)
- 保障部分のコスト(約5%)
つまり、払込保険料の約20〜30%は保険会社の取り分なのです。
つみたてNISAなら?

- いつでも引き出しOK
- 元本割れリスクはあるが、10年以上の長期なら高確率でプラス
- 手数料は年0.1〜0.5%程度(保険の1/20以下)
デメリット③:インフレに弱い(お金の価値が目減りする)
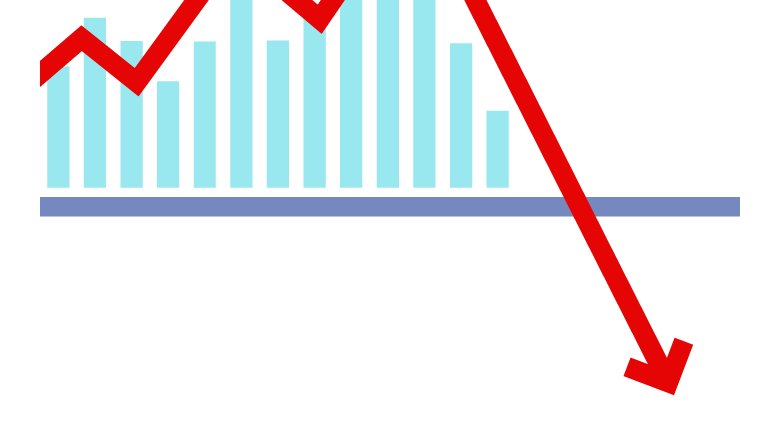
18年前(2007年)と今(2025年)で物価はどう変わった?
物価・学費の上昇比較(2007年→2025年)
| 項目 | 2007年 | 2025年 | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 大学初年度納付金(私立) | 約130万円 | 約150万円 | +15% |
| 消費者物価指数 | 100 | 約115 | +15% |
| ガソリン(1L) | 120円 | 170円 | +42% |
学資保険の返戻率が102%でも、実質的には約13%マイナス
18年後に220万円もらっても、物価が15%上がっていたら実質的な価値は約191万円になってしまいます。
つみたてNISAなら?
株式市場は長期的にインフレ率を上回る成長を続けています。過去30年の日本株の平均リターンは年約6%(インフレ調整後でも年4%程度)。
デメリット④:手数料が異常に高い(年2〜3%)
学資保険の隠れた手数料を暴露
「4万円の利益」の裏側にある驚愕の真実
⚡ 衝撃の事実
あなたが得た利益:4万円
保険会社が得た利益:80万円
つまり、運用益の95%は保険会社の取り分。
あなたの取り分はわずか5%です。
つみたてNISAの手数料は?
投資商品の手数料比較(年率)
| 商品 | 手数料(年率) |
|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 0.05775% |
| 楽天・全米株式インデックス | 0.162% |
| 学資保険(実質手数料) | 約2〜3% |
手数料の差は約50倍!
デメリット⑤:資金拘束されて機会損失が生まれる
18年間、お金が自由に使えないというのは想像以上に大きなデメリットです。
よくあるシナリオ:
- 子どもが10歳のとき:急に私立中学受験を決意 → 塾代50万円が必要
- 学資保険を解約すると:120万円払って90万円しか戻らない(▲30万円)
- 結局:教育ローンを年利3%で借りることに…
つみたてNISAなら?
- いつでも必要な分だけ引き出せる
- 値動きリスクはあるが、10年経過していればプラスの可能性が高い
- 余裕資金として他の投資や急な出費に対応可能
実体験:学資保険を解約して20万円損したけど正解だった理由
私の学資保険の詳細
学資保険 具体例(子ども0歳から18年間)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加入時期 | 2015年(子ども0歳) |
| 月額保険料 | 10,000円 |
| 満期 | 2033年(18年後) |
| 返戻率 | 102% |
| 満期金 | 約220万円 |
2020年に解約を決意(5年経過時点)
学資保険 払込総額・解約返戻金
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 払込総額 | 60万円 |
| 解約返戻金 | 40万円 |
| 損失 | ▲20万円 |
「20万円も損するなんて…」と悩みましたが、解約を決意。
解約後、つみたてNISAで運用(2020〜2025年の5年間)
積立投資の例(5年間)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月額積立 | 10,000円 |
| 積立期間 | 5年(60ヶ月) |
| 積立総額 | 60万円 |
| 2025年の評価額 | 約78万円 |
| 利益 | +18万円 |
2033年まで継続した場合の比較
| 項目 | 学資保険継続解約 | つみたてNISA |
|---|---|---|
| 2033年の金額 | 220万円 | 約320万円 |
| 実質利益 | +4万円 | +124万円 |
| 差額 | +120万円 | |
結論:20万円の損失を出しても、長期的には100万円以上得をする
貯蓄型保険 vs つみたてNISA 徹底比較
学資保険 vs つみたてNISA
学資保険とつみたてNISAの比較(18年間)
| 比較項目 | 学資保険 | つみたてNISA |
|---|---|---|
| 月額 | 10,000円 | 10,000円 |
| 期間 | 18年 | 18年 |
| 払込総額 | 216万円 | 216万円 |
| 18年後 | 220万円 | 約350万円(年5%想定) |
| 利回り | 年0.1% | 年5% |
| 税金 | 満期金に課税の可能性 | 完全非課税 |
| 途中解約 | 元本割れ | いつでも可能 |
| 手数料 | 実質年2〜3% | 年0.1〜0.5% |
| インフレ対応 | ✕ | ◎ |
| 柔軟性 | ✕(18年間拘束) | ◎(いつでも引き出し可) |
終身保険 vs つみたてNISA+掛け捨て保険
終身保険のプラン例:
- 月額保険料:20,000円
- 払込期間:30年(総額720万円)
- 解約返戻金(30年後):約780万円
- 死亡保障:500万円
つみたてNISA+掛け捨て保険:
- つみたてNISA:月15,000円
- 掛け捨て定期保険:月5,000円(死亡保障3,000万円)
終身保険とつみたてNISA+掛け捨ての比較(30年間)
| 比較項目 | 終身保険 | つみたてNISA+掛け捨て |
|---|---|---|
| 月額 | 20,000円 | 20,000円 |
| 30年後の資産 | 780万円 | 約1,240万円 |
| 死亡保障 | 500万円 | 3,000万円 |
| 差額 | +460万円 | |
解約すべきか判断するチェックリスト
こんな人は今すぐ解約を検討すべき
- 加入してから5年以内(損失が少ない)
- 返戻率が105%未満
- 月額保険料が1万円以上
- 満期までまだ10年以上ある
- 家計に余裕があり、投資に回せる
解約しない方がいい人
- あと2〜3年で満期を迎える
- 解約返戻金が払込総額の90%以上
- 投資は絶対にしたくない
- 元本割れが精神的に耐えられない
解約後の3ステップ行動プラン
STEP1:解約返戻金を確認する
保険会社に電話またはWebで「今解約したらいくら戻るか」を確認しましょう。
確認方法:
- 保険会社のお客様センターに電話
- Webサイトのマイページで確認
- 証券番号と本人確認情報を用意
STEP2:つみたてNISAの口座を開設する
おすすめ証券会社の特徴比較
| 証券会社 | 特徴 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 楽天証券 | 楽天ポイントが貯まる、初心者向き | ★★★★★ |
| SBI証券 | 取扱商品が最多、手数料最安級 | ★★★★★ |
| マネックス証券 | サポートが充実 | ★★★★☆ |
口座開設の流れ:
- Web申込(10分)
- 本人確認書類アップロード
- 初期設定(つみたてNISA選択)
- 約1週間で開設完了
STEP3:積立設定をして放置する
おすすめ商品:
投資信託の手数料とリスク比較
| 商品名 | 投資先 | 手数料 | リスク |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 世界中の株式 | 0.05775% | 中 |
| 楽天・全米株式インデックス | 米国株式 | 0.162% | 中〜高 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産) | 株式+債券 | 0.143% | 低〜中 |
積立設定したら、あとは放置するだけ!
月1回チェックする程度で、日々の値動きに一喜一憂しないことが成功の秘訣です。
よくある質問(FAQ)

- Q1. 元本割れしてまで解約する意味はある?
-
A. 長期的に見れば、解約した方が得になるケースがほとんどです。
具体例:
- 今解約:20万円の損失
- このまま継続:18年後に4万円の利益
- 解約してつみたてNISA:18年後に124万円の利益
- 差額:120万円
「もったいない」という感情より、「これからの利益」を考えましょう。
- Q2. 貯蓄型保険にメリットは全くない?
-
A. 以下のような人には向いているかもしれません。
貯蓄型保険が向いている人:
- 投資は絶対にしたくない
- 元本割れが精神的に耐えられない
- 強制的に貯金できる仕組みが必要
- すでに満期まで2〜3年
ただし、これらに当てはまる人でも「国債」や「定期預金」の方が手数料が安くおすすめです。
- Q3. つみたてNISAって元本割れしない?
-
A. 短期的には元本割れするリスクがあります。
過去のデータ:
- 5年間の保有:元本割れの確率 約20%
- 10年間の保有:元本割れの確率 約5%
- 15年間の保有:元本割れの確率 約1%
- 20年間の保有:元本割れの確率 ほぼ0%
結論:18年間の学資保険の代わりなら、つみたてNISAの方が期待リターンが圧倒的に高い
- Q4. 保険の営業マンに「損する」と言われました
-
A. 営業マンは保険を売るのが仕事なので、当然引き止めます。
よくある営業トーク:
- 「今解約すると元本割れして損ですよ」
- 「あと○年で元が取れます」
- 「投資は危険です」
冷静に判断するポイント:
- 営業マンの言う「損」は今の時点だけの話
- 長期的な機会損失を計算していない
- つみたてNISAとの比較をしていない
第三者のFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのがおすすめです。
- Q5. 学資保険を解約したら、教育資金はどうすればいい?
-
A. つみたてNISA+貯金の2本柱がおすすめです。
具体的なプラン:
資金用途と運用方法 資金用途と運用方法
用途 金額 運用方法 大学資金(18年後) 月10,000円 つみたてNISA 緊急予備費 50万円 銀行預金 中学・高校の塾代 月5,000円 銀行預金 ポイント:
- 18年後に必要なお金→つみたてNISA
- 5年以内に使うお金→銀行預金
関連記事で家計をさらに最適化
おすすめ記事
保険料を年間12万円削減!30代40代が絶対に知るべき保険見直し完全ガイド
貯蓄型保険だけでなく、医療保険・生命保険も含めた総合的な見直し方法

楽天カード×マネーフォワード連携が最強な理由を徹底解説!年間36万円節約した秘密を公開
手入力ゼロで家計簿を自動化して、節約効果を最大化

クレジットカード家計簿のズレを完全解決
月1万円のムダを発見する管理術

まとめ:貯蓄型保険は今すぐ見直すべき
貯蓄型保険の5つのデメリット
- 利回りが低すぎる(年0.1〜0.5%)
- 途中解約で元本割れする
- インフレに弱い
- 手数料が異常に高い(実質年2〜3%)
- 資金拘束されて機会損失
つみたてNISAとの差額
学資保険とつみたてNISAの18年間比較
| 期間 | 学資保険 | つみたてNISA | 差額 |
|---|---|---|---|
| 18年後 | 220万円 | 約350万円 | +130万円 |
今日からできる3つのアクション
- 保険会社に解約返戻金を確認する
- 証券会社でつみたてNISA口座を開設する
- 月10,000円の積立設定をして放置する
「元本割れが怖い」という感情より、「これからの100万円の差」を考えましょう。
貯蓄型保険を解約してつみたてNISAに切り替えるだけで、あなたの子どもの教育資金は大きく変わりますよ。